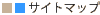レポート
第6分科会 |
アジアのナショナル・トラスト |
台湾や韓国をはじめ、アジアのナショナル・トラストの現状を報告。アジアが抱える問題点や今後の活動について討議し、アジアのナショナル・トラスト・ネットワークを発足させましょう。 |
進行役
|
・台湾のEnvironmental Trust Foudation
(ETF)について
(ETFスタッフのCocoさんによる説明)
2000年4月に設立したばかりで、現在は毎日 Environmental News という国内・外の環境問題についてのE-paperというニュースの配信をしている。E-Paperとはメーリングリストのようなもので、紙を無駄にしないために電子情報での媒体である。中国・台湾では環境問題についての認識が低い。中国や台湾でNT活動をアピールするきっかけが作れないか?と考えている。30歳以下の8人のスタッフで構成されている。まだ財源はなく、スタッフは無給・ボランティア。連絡先は会長の自宅となっている状況。
ETFのスタッフ Cocoさん(中央)
・韓国のナショナル・トラストについて
・KBS(韓国放送公社)で今年制作された、韓国・イギリス・日本のNTの現状についての番組「緑を夢見る」というビデオの上映
内容:韓国のナショナル・トラスト運動は「国民信託運動」と訳されている。
無等山(ムドゥンサン)等、各地で土地の買い取り運動が行われている。
「みどりの連合」というネットワーク組織があり、一口3万ウォン、230人で700坪の土地を買い取った。子供の名前で登記したものの、土地収用法による問題がおきた。
現在、ソウルにあるNational Trust of KOREA(自然環境の保護が主)
大田(テジュン)にあるNational Trust for KOREA(人文遺産が主)の2団体がある。
・朴さんの紹介
1ヶ月前にソウルの韓国ナショナル・トラストの時期事務総長になることが決まり、趙さんとともに現在日本のナショナル・トラストについて研究している。
・韓国NTの紹介
2000年1月に設立されたばかりで、国内のNT的運動の調査を行っている段階。
インターネット上で買い取りの候補地を募るコンテストを行っている。(選考基準があいまいなところに問題があるのでは、との意見があった)国内ではNTの知名度は低いので、普及・啓発が一番の目的。インターネット上のコンテストの賞品は企業が提供している。会は会員による会費による運営というよりは、企業がスポンサーとなっている。インターネット以外でもKBSや朝鮮日報などの媒体がバックアップしており、活動を紹介している。
役員は50人程度の学識者で構成されている。名ばかりで活動フィールドがない所に問題がある?
朴さんの個人的な見解:
・今後の活動としては、今回の大会での富士山・柿田川の見学会のような自然観察会を行ったり、日本のNTの全国大会のような会を開催したい。
・日本のように必要性があり設立されたのではなく、このような「ナショナル・トラスト協会」がまずありきと設立されたので、トップダウン式になってしまっているところに問題があるようなきがする。地域の活動団体からボトムアップ式ではない、やや中央集権的なところがある。(地域に根差していないのでは?との意見があった。)
韓国のNT日本の社団NTのような各地の活動の連合体のような組織をめざすのはどうか(高砂)
イギリスではひとつのナショナル・トラストがプロパティをすべて抱えている状態。組織同士のネットワークで構成されているのが、アジア的トラストなのではないか。(藤田)
財団法人ナショナルトラストについて:(山岡氏)
財団では5つのプロパティを持ち、NTだけでなくシビックトラストの手法も取り入れ、ヘリテイジセンター等での地域おこしに協力している。その他、鳴き砂などのイベントを行っている。運営面では財政での問題を抱えている。
その他アジアのNTについて:
王俊秀さんがANNTという団体を組織している。メーリングリストの活動が主体で実態はない。2001年にアジア大会を行いたいと考えている。
アジアのナショナル・トラスト同士の交流事業について
・お互いのプロパティの視察
・広報活動・インターネットを利用した情報の共有・公開
・ワーキングホリディのような、プログラムを使った交換留学制度(イギリスの事例を参考に)
イギリスでは Aecon等活動プログラムがしっかりしている。韓国での活動に生かしてみればどうか。(高砂)
教育の現場から:日本において次世代への広報活動として NTはどの教科にも属さない、学際的な言葉として扱われており、「総合的な学習」の分野になっている。学校の先生も知識がないのでもっと働きかけが必要である。(福田)
富士山 NTでは研修を通して人を育て、環境問題への関心を根付かせようと考えている。砂漠化が進行しているという中国でNT運動の余地はあるのだろうか。(保坂)
活動を細く長く、国境を越えて、後の世代まで NTの活動を引き続けていくことに意味がある。(高砂)
NPO・NGOのスタッフ同志の交流や国民同志の交流に、インターネットを通した情報の共有はとても有効なのではないか?日・韓・台のインターナショナルなホームページを開設したい。
ボランティアするということへの意識の違い(ヨーロッパ/アジア)があるのではないか(藤田)
日本は外来語をそのまま使うのに、その言葉の本来の概念が正しく使われていない、内容があいまいになってしまっている。たとえばアセスメントなどの言葉。(趙)
ナショナル・トラストという共通語
韓国では NTを「国民信託運動」と訳している。また「みどりの連合」では「土地を一坪買おう運動」という名で展開している。アジアでナショナル・トラスト運動を表す共通語を作れないだろうか?(藤田)
国によって事情も異なり、それは難しいのではないだろうか。(西川)
ナショナル・トラストという名前はそのままで、各国の事情にあった活動を展開していくべき。イギリスを本家とする NTの精神こそが重要・NTの精神がまず最初にあるべきで、ファンダメンタルな問題(お金など)はそれからである。
ホームページにアジアのトラストニュースをつけるようにする。情報の交換やコラム等つけて、その国の言葉に変換して発信するのはどうか(西川)
アジアといってもひとくくりにはできないが、モンスーン気候という原風景を同じくする国同志で共通する部分があるのではないか(丹下)
言語の壁が問題が第一。今後解決していくべき問題。(難波田)
その他
韓国・台湾以外のアジアの国の事情について:インドネシアの事情について(参考文献:岩波新書『地球環境学』) ODAによる援助は政府間のやりとりで、企業に使われるころが多く、地域に行き渡らない。地元の人たちにジャングルの砂漠化が進んでいるということへの理解があまり得られない。ハルク島に環境教育施設を建設中といい、地域の人たちの環境保護への意識が高まることを期待している。(丹下)
韓国の東江の保護運動などには柿田川の保護と共通するものを感じた。(宇野)
協会のホームページについて:子供向けホームページを作って欲しい。写真が大きすぎてリンクが少なく、更新が遅いので改善して欲しい。これからの時代ホームページでの発信やそのコンテンツの充実は必須となってくる。(福田)
分科会風景
まとめ
・インターネット上での活動・情報の公開。基本は英語で、将来的には各国の言語でインターネットで流したい。
・お互いその国の独自の文化にあった活動、その国流の解決方法を模索しなくてはいけない。しかし NTの本来の精神は共通しており、国をこえたアジアのネットワークを利用して、NTという言葉を広めたい。