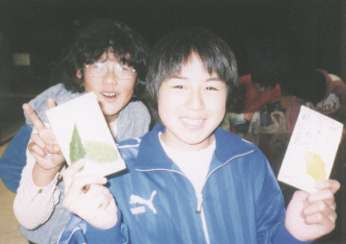|
第8分科会 |
子どもたちのための入門講座 |
|
子ども向けの柿田川観察会。柿田川の素晴らしい環境の中で楽しんだあとは、ナショナル・トラストのマンガやネイチャーゲームで遊びましょう。子どもだけでも、大人だけでも、親子での参加も、みーんな大歓迎です。 |
進行役
|
|
「入門講座って、なんの入門講座か知っている人?」と最後に参加者のみんなに聞いてみたら、知っている人がいなかった。まあそれでもいいか。9時半からの3時間、飽きることなく子どもたちと楽しんだので。参加者には、地元のみどりの少年団の子どもたちが多かった。進行役は柿田川みどりのトラストの細倉さんです。自然観察解説にはとても慣れていらっしゃる、植物の専門家です。植物だけでなく、先生をしていらっしゃるので、子どもたちとのやりとりにも愛情がたっぷり。子どもの才能の目を摘まないように、何を見せても「すごいの見つけたね、すごいねぇ」という細倉さんこそすごい! |
|
|
|
観察のコースは簡単。まずは福祉センターの2階のホールで集合。そこで細倉さんから「2つの宿題」が出ました。葉っぱを拾うこと、それからどんぐりを3つ拾ってくることです。柿田橋の上から川をながめた後、橋のわきから川に降りて、やませみの巣穴や藻を観察しました。アメリカセンダングサがいっぱいあって、みんな身体中の洋服にくっついた。コセンダングサをよおく観察しました。どうしてこんなにくっつくのかな。逆向きの小さなとげのようなチクチクが、くっつく理由のようでした。 次に、細倉さんはある葉っぱをとって、それをもんでみんなに匂いをかがせました。「これを臭いと思う人」と聞いたら、10人ちょっといました。反対に「いい匂いだと思う人」と聞いたら、また10人ちょっといました。でもこれは「クサギ」というそうです。きっとこの名前をつけた人は臭いと思った人だったのでしょう。今回は引き分けだったので、もし臭くないと思う人がこれを発見したとしたら、どうなっていたかな。「イイニオイギかな?」と誰かが言いました。 |
|
もう少し川沿いを歩き、クルミの木の下で落ちているクルミの実を拾いました。採ったクルミの実を川の水で洗う子もいました。ミントを摘みました。ヒンジモとミシマバイカモとナガエミクリとカワジシャ※の違いを勉強しました。「カワニナとったよ」という女の子もいました。カラスウリを採る人もいました。ミシマバイカモは、きれいでしかも流れている水でしか育たないので、この川をいつまでも守っていけたらなと思いました。 福祉センターでは、押し葉とやじろべえと竹笛を作りました。押し葉は、はがき大の厚紙に、紅葉できれいになった葉っぱを載せ、さらに自分なりのアレンジで葉っぱに穴をあけたり、葉っぱの周りに絵を描いたりして、上をビニールの粘着シートで覆いました。オリジナルカードのできあがりです。やじろべえはなかなか難しい。まずはろうそくの火の上で、竹ひごの中心をあぶって湾曲させます。それをやじろべえの中心にして、そこに錐で穴を開けたどんぐりを3つ、中心と左右に差します。きちんとやじろべえらしく振れるものと、なんだかまっすぐのままのやじろべえなどもありましたが、どれも愛嬌のあるものになりました。 |
|
|
|
そしてついに竹笛です。これはつくったというよりは、細倉さんが前の晩、用意してくださった、切り込みの入った竹の筒に、フィルムを差し込み、それを竹の口の形に沿って切り取るだけ。口でくわえて思いっきり吹くと、・・・「ぶーっ」というおならのような(すいません。でも本当なのです)大きな音が出ます。太い竹からは低い音が、細い竹からは高い音が出ました。みんながおもしろがっていっせいに吹くので、部屋中大きな音が響きわたりました。とてもにぎやかです。笛ができたので、みんなで記念撮影。ナショナル・トラストマンガ「おじいさんの森」をおみやげにプレゼントしました。子どもたちから学ぶことの多かった、あっという間の3時間でした。 (記録:社団法人日本ナショナル・トラスト協会 進士万里子) |